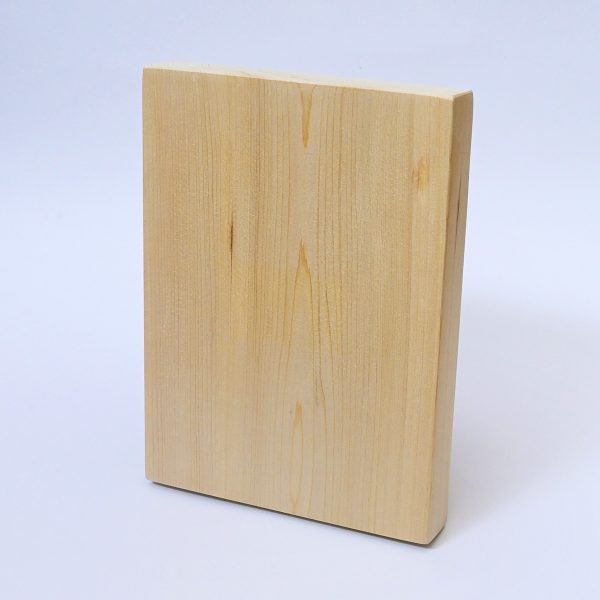絵本から得られるもの
絵本を読むこと、読み聞かせること、こんなことをじっくり考えるなんて、ひまな人だろうと思われるかもしれませんが、世の中のお父さん、お母さん、または子どもに関わる人たちにどうしても伝えたくて、分かりきったことかもしれませんが、時間を割いて読んでいただけたら、とても嬉しく思います。
プロフィール :
横井ルリ子さん 教育者教員経験を活かし、個人教授という立場で長年教育に携わる。現代の教育に疑問をもち「母のクラス」「こころのクラス」など独自の教育法を実践。最近は、読み聞かせ、読書、作文など国語教育にも力を入れている。在港16年。
『坊っちゃん』
どんぐりころころ どんぶりこ
おいけにはまって さあたいへん
どじょうがでてきて こんにちは
ぼっちゃんいっしょに あそびましょう
子どもが小さい頃、この歌が大好きで、いつも二人の娘と歌っていた。私たちは、家でも公園でも旅先でも辺り構わず日本の歌を歌う習慣がついていた。だって、私は日本の歌しか歌えないのだから。
私の夫は香港人。でも彼はあまり中国語の歌(童謡)を知らない。メロディーは知っていても、歌詞を正しく記憶しているものは皆無に等しい。よって娘たちは私の手によって、どんどん日本化されていった。
ある日、私たちがいつものように「どんぐりころころ」大合唱をしていると、夫が真面目な顔をして、「ねえ、そのさあ、ぼっちゃんって誰のことなの?」と 質問してきた。彼は何度聞いても、どれだけ考えても、どんな名前の子かわからないと言う。簡単な日本語なら聞き取れる彼の自尊心が少し傷ついていたかもし れない。だが、私たちは顔を見合わせて大爆笑した。夫は「のりひと」がのりちゃんとか「えりこ」がえりちゃんとかのように坊ちゃんは誰かの名前の愛称だと 思っていたらしい。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。まあ、ずっと胸中にしまってあった謎が解けてよかったではないか。
夫には「ぼっちゃん」とは、少しレトロな言い方だが、男の子の呼称であるとしか説明していないが、私たちは日本人、『坊ちゃん』 と言えば夏目漱石である。私は世に出ている作家の中で、一番彼が好きだ。本の内容も文体も、顔も全部大好きだ。私と漱石との出会いは、確か小学4、5年生 ぐらいのときだった。いつも行く小さな書店の店先で『我輩は猫である』の背表紙を見かけた。猫好きだった私はその本をどうしても買いたくなった。幼い私は 我輩というからには、この本には猫の本音が書かれていると思い込んでいた。家へ帰り、急いでページをめくった。難しい。読めない漢字が大部分を占めてい た。とても2ページ目をめくるに耐えられなかった。こうして私の『我輩は猫である』は今だ読まれることもなく実家の本棚に眠っている。
その後長らくごぶさたしていた漱石の作品に遭遇したのは、中学生の国語の教科書。『坊ちゃん』だった。漱石特有の歯切れのよい文体に胸が躍った。読み物 として掲載されている『坊ちゃん』は、テスト範囲に含まれないという理由で生徒たちは軽く見ていた。私はこんな面白い作品を精読しないなんてもったいない と一人で思っていた。
今年の春も、例年通り、うちに居候さくらが修業にやってきた。どんな話の流れだったのかはっきりとは記憶していないが、夏目漱石の話題になった。私は 「それでさあ、さくら、夏目漱石読んだことある?」と尋ねると、無邪気に「誰?それ?」と答えるではないか。私は一瞬耳を疑った。さくらは一応日本人の女 子高生だ。日本の高校へ通い、曲がりなりにも現代国語などを勉強している身分だ。私は「さくら、『坊ちゃん』を書いたさあ…前の千円札にのっていた人でさ あ…ひげを生やしていて…」私が思いつくありったけの情報を与えたが、彼女は「その人有名なの?聞いたことない!」悪気もなく言い張った。この一言が命取 りになった。
まもなく判決はくだされた。今年の夏休み、さくらは松山へ連行される。
坊ちゃんを生んだ松山の地で、我々は『坊ちゃん』を漱石の直筆で読んでみようと考えている。そこで、さくらが私とは違う何かを感じてくれたら…そう願ってやまない。
2009年5月26日の日記より
*『直筆で読む「坊ちゃん」』 夏目漱石 集英社新書