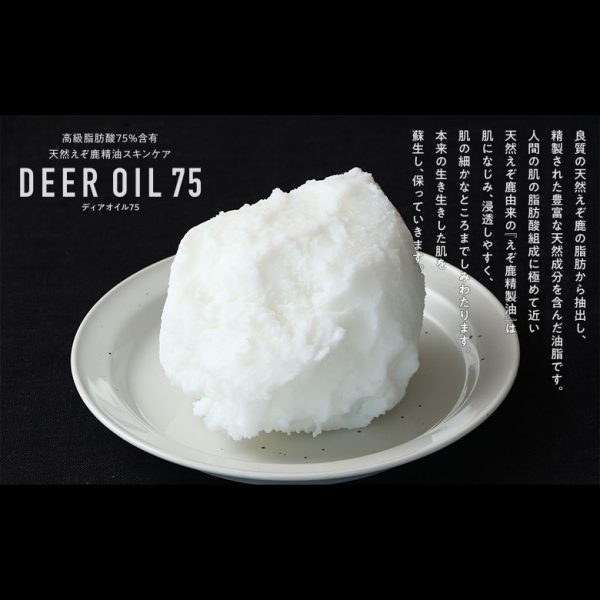絵本から得られるもの
絵本を読むこと、読み聞かせること、こんなことをじっくり考えるなんて、ひまな人だろうと思われるかもしれませんが、世の中のお父さん、お母さん、または子どもに関わる人たちにどうしても伝えたくて、分かりきったことかもしれませんが、時間を割いて読んでいただけたら、とても嬉しく思います。
プロフィール :
横井ルリ子さん 教育者教員経験を活かし、個人教授という立場で長年教育に携わる。現代の教育に疑問をもち「母のクラス」「こころのクラス」など独自の教育法を実践。最近は、読み聞かせ、読書、作文など国語教育にも力を入れている。在港16年。
小さな小さな科学
「もやし くださーい。」
市場の小さな小さな八百屋さん、私の行きつけのお店である。菜っ葉にトマトにきゅうり、所狭しと並べられた店先にもやしは見辺らない。
以前、私は、このお店で、もやしを買っていく人を見かけた。私が到着した時には、既に袋に入れられ、お客さんはお金を払っている場面だった。もやしはどこにあるのだろう。今日は思い切って自分でもやしを買ってみることにした。
「もやし、どれぐらい欲しいの?緑豆か黄豆どっち?」
おじさんは私に質問をした。私は、もやしに種類があることを全く知らなかった。緑か黄なんて・・もやしは白いでしょうに・・私は緑豆を買ってみることにし た。おじさんは、棚の下からおもむろに口がしっかりしばられた黒いポリ袋を取り出した。もやしはそこに入っていた。(すごい!ここは青空市場だ。日中は太 陽の光がサンサンとふりそそぐ。棚の上になんか置いておいたら、もやしが全部光合成をしてしまい、緑色になってしまう。緑豆のもやしは、私が想像していた 普通のもやしだった。黄豆の方も少し気になる。
私は翌日再び八百屋さんに通った。今度は黄豆を買うことにした。やっぱりあの黒いポリ袋に入っていた。黄豆もやしを受け取った。よく観察してみると、 何のことはない、豆もやしだった。そうだよね、私も、もやしと、豆もやしなら知っている。この八百屋さんのもやしは、私がよく見かけるスーパーの袋もやし と違い、ポリ袋の中で放っておいたら、発芽してしまった、という感じだ。ひげ根がくるんと巻いておりとても自然な成長振り。これを見て私は、うちで作れる と実感した。
翌日、私は、再び市場へ向かっていたが今度は、緑豆を買うためだ。もやしを自分で作るのである。私は思い立ったら、すぐに実験したくなる質で、これまで も たくさんの 家庭内実験を試みてきた。ちょうど 甥(6才)と姪(2才)が来ていたので、一緒にもやしを育てることにしたのだ。娘も以前、もやしを育 てたが、毎日、日に当て、水もたっぷりやって、愛情をそそいでいた。そろそろ食べごろだといってもせっかく育てたのだからもやしが青々とした双葉をつけ、 かいわれ大根のようになっても食べさせてくれなかった。しかし、涼とあすかは、まさに食べるために育てるという精神で取り組んでおり、私が、「もやしは日 に当てると緑色になってしまうので、日陰で育てた方がいい」と言うと、即座にソファの下に置いた。3~4日でひげ根がでてきた。二人の第一声は「わぁー。 おいしそう!」だった。
昨今、子どもたちの科学離れが叫ばれている。大学の工学部の方が、法学部や経済学部より偏差値が低いという現像まであるという。 私たちの時代には 「あり得ない」ことだった。先日の新聞で 私が小学生の時 愛読していた 「学習」と「科学」休刊という記事が目に入った。売り上げが ピーク時の10分の1に落ち込んだこととインターネットの普及により、読者のニーズに合わなくなったという理由らしい。何とも淋しい話である。またひとつ 私の子ども時代を娘に語るネタが姿を消していった。
「科学」を難しく考える必要は全くない。日常生活の中にたくさん埋もれている。インターネットで得られる情報は机上の空論に過ぎないのだ。実験・観察がこそが子どもにとって何よりの肥やしとなるのだ。それらなくして、発見、発明は得られない。
藤原賞を受賞した名城大教授飯島澄男氏はこう語る。「科学とは、なぜなの?と疑問を持ち、現象をよく見て分析したり、実験したりして理解することだ。すべては観察から始まる。」
師走。涼太郎とあすかへ。今年のクリスマスプレゼントは、もやしキット。早速本日発送いたします。小さな小さな科学をお楽しみください!
*「学習」、「科学」 学習研究社
2009年12月9日
ある日の日記より