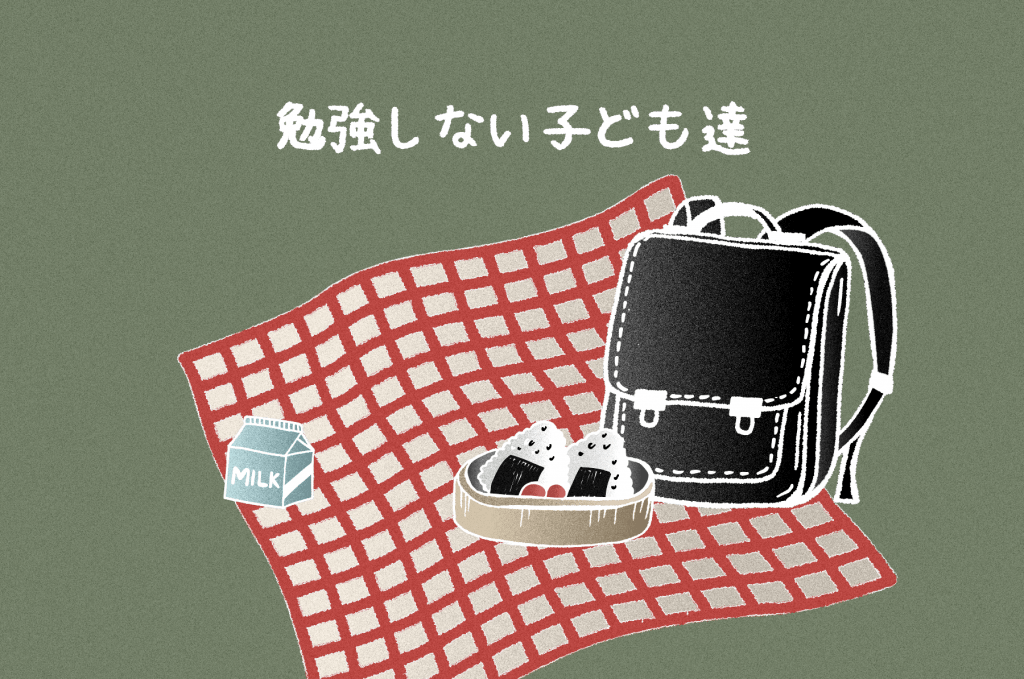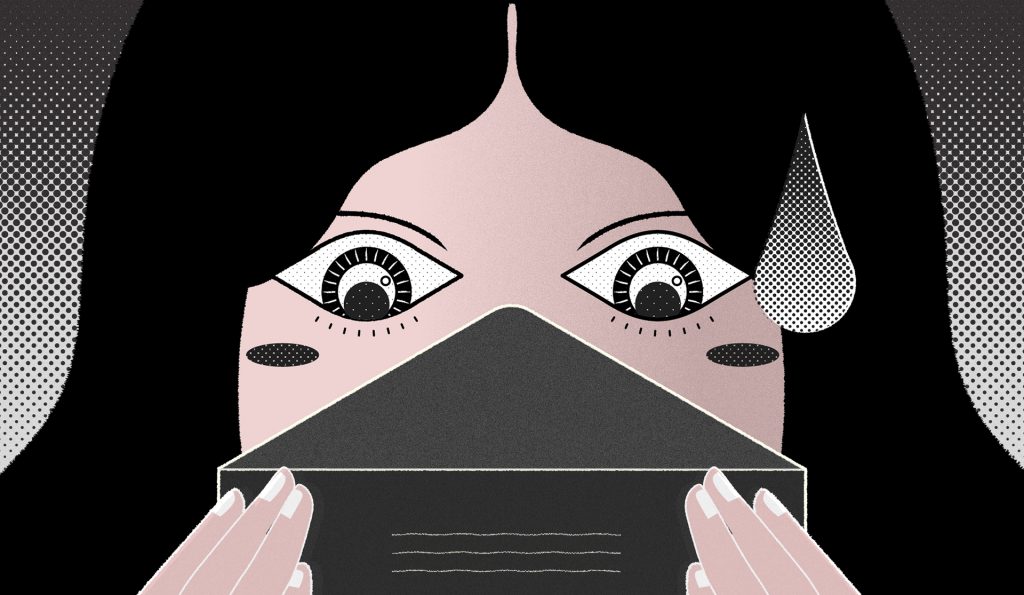香港子育て回顧録 -これまでも、これからも
白井純子
愛知県出身。大学では日本国文学科専攻。北京電影学院留学中に香港人である現在の夫と出逢う。長男を東京で、次男を香港で出産。
2014年夏に9年間暮らした香港から大阪に帰国。帰国後に保育士資格とチャイルドマインダーの資格を取得。
2019年夏から息子達の留学のためバンクーバーに滞在中。現在の関心ごとは「Sustainability」。
新しい文化との共存
人は常に自分を基準にして物事を判断してしまう。時はただ先へ先へと流れているにもかかわらず、自分が経験した時代の常識を引きづりがちだ。若かった頃に「今時の奴らは…」と聞くと、年寄りの僻みにも聞こえたが、気がつくと自分も時代の波の最先端から少し遠のいたところにいる。日々の生活で頭がいっぱいの世代は、新しい文化を作り出す時間的、精神的余裕はないのかもしれない。いや、ここまで築いてきた自分の中の常識を壊すことに怖気付いてしまうのかもしれない。とにもかくにも、子ども達からもたらされる新しい刺激にひどく感嘆し、なんだか言葉通り「目からうろこが落ち」たような気分を先日味わった。
私はかねてから、子どもにゲームをさせることには反対の立場を取ってきた。今月、小学6年生の子どもがゲームを取り上げられて包丁を振り回すという事件も起きた。世界保健機関(WHO)も国際疾病分類で「ゲーム障害」を依存症の一つと位置付けている。依存症によって自分の欲望をコントロールできないような状況が子どもの頃から起こるなんて、人生を台無しにしかねない。しかしこのご時世、子ども達にゲームを強制的に禁止することで友人との遊び方に影響が出てくる。ゲームをしない子どもの方が少数派になった時代、頑なに拒み続けることが果たして我が子のためになるのだろうか。戸惑いながらも、遊ぶ時間のルールを必ず守るという約束のもと、ついに我が家でもゲームを解禁してからもう直ぐ1年になる。
今までは、遊び始める前に「今から20分やるよ」と声をかけられ、「OK」と答えるだけの繰り返しだった。約束の時間をオーバーした時には注意をし、約束を守れなかった時には1週間遊ばせないという罰を与える、監視官のような役割を担っていただけ。ところが最近、子どもたちがゲームの中の自分のアバターを私に見せに来て、「この服装と、この服装のどっちがいいと思う?」などと意見を求められたり、世界中から参加者が集うゲームの試合結果などを報告してくれるようになったり、今まで意識的に遮断していたゲームの世界がぐっと身近になった。
そんなある日、長男が私にヘッドフォンを付けて「聞いて」と言う。私は目を瞑ってその音楽に集中した。まるで映画音楽のような、世界観のある美しい曲だった。聞いていると目の前に映像が浮かび上がってくる。「すごく素敵だと思う。」と私が伝えると、長男は嬉しそうな顔をして、これを作曲したのが人気のあるクリエーターであることや、ゲームの中で流れる音楽をたくさん作っていることを教えてくれた。私たち世代にとって音楽はCDを買って聞くものだったが、今は違う。一人のクリエーターが作り出すメロディに一番適した声の歌手をあてがって作品にし、ゲームのバックで流したり、映像と一緒にYouTubeで流したりすることで世界中に発信される。今まで知らなかった新しい才能や文化の存在に気づいてハッとした。拒み続けていたなら、こんな芸術に出会えなかったのかもしれない。悲しいかな最近は、新しい感動を味わう機会は減る一方だ。
知らず知らずのうちに、自分が経験しかなった「ゲーム」や「YouTube」といった新しい文化に偏見を持ち、私の想像を超えてそこに広がっている世界から目をそらしてきた気がする。一旦作り出された文化は、時代とともに生き物のように成長し形を変えていく。それを吸収し影響を受けた世代がまた、新たな文化を創造していくのだ。
ゲームは依存症になる。現実社会で生きられない人間を作ってはいけない。それは大人の責任だ。その一方で、ゲームの世界にはすでに新しい文化が息づいている。刻々と成長を続け、時代の波の先へ先へと競い合うクリエーター達がしのぎを削っている。これも無視できない。新しい文化に対する偏見と無知で子ども達の可能性に水を差さないよう、常に柔らかな感受性を持ち続けたいものである。
Powered by Froala Editor