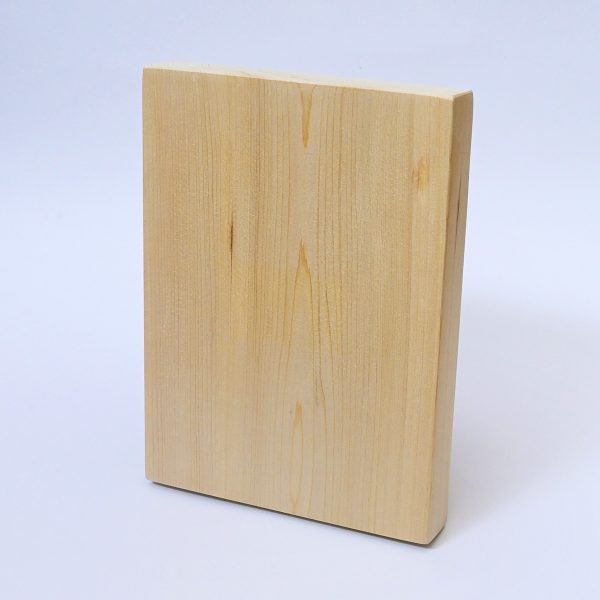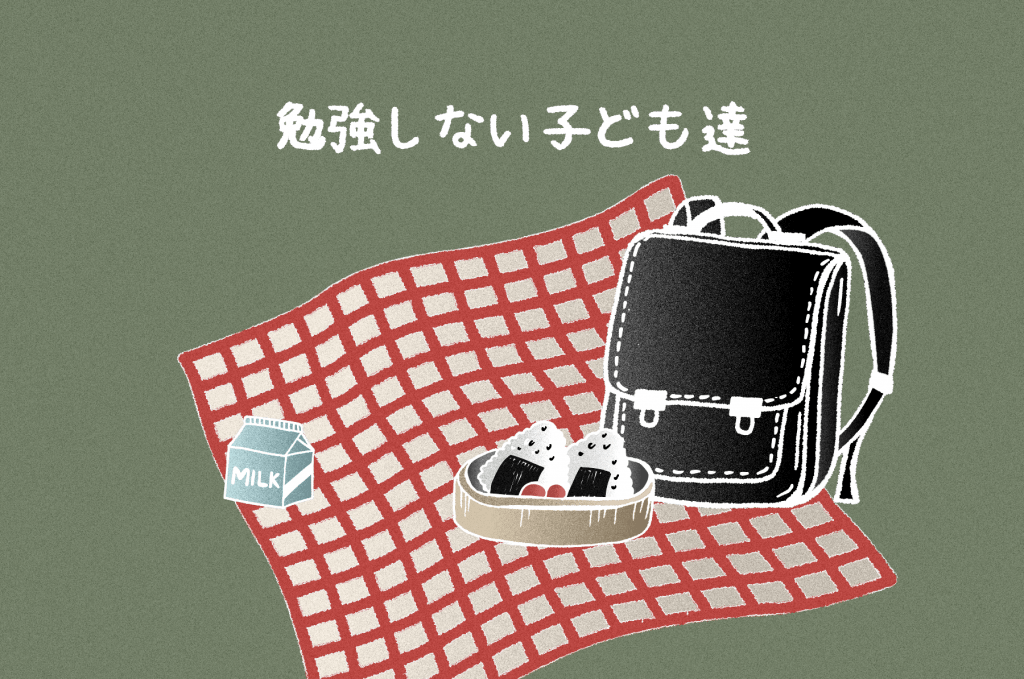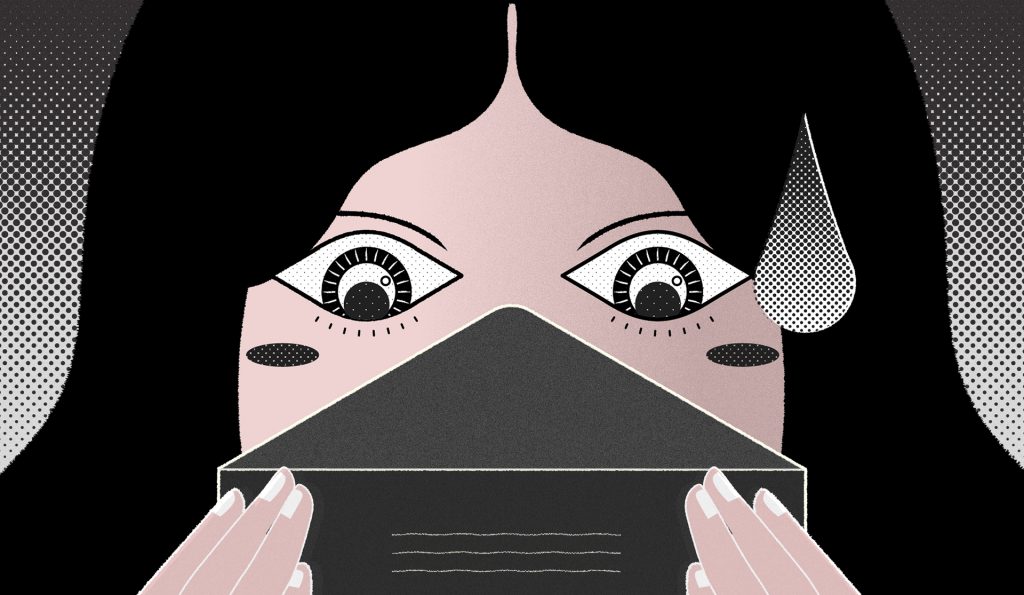香港子育て回顧録 -これまでも、これからも
白井純子
愛知県出身。大学では日本国文学科専攻。北京電影学院留学中に香港人である現在の夫と出逢う。長男を東京で、次男を香港で出産。
2014年夏に9年間暮らした香港から大阪に帰国。帰国後に保育士資格とチャイルドマインダーの資格を取得。
2019年夏から息子達の留学のためバンクーバーに滞在中。現在の関心ごとは「Sustainability」。
新しい生活
真っ青な空に赤い楓の旗がはためく。広い遊び場とつながった学舎のあちらこちらから子ども達の声が聞こえてくる。次男の小学校はスクールバスがないため、3時になると保護者が迎えに来るのだが、その半数近くが父親であることに驚いた。どんなお仕事をしている人たちなんだろう…子育てを母親任せにしない文化って素晴らしいなあと一人感心した。夏の終わりの眩しい日差しの中、緑が映える芝生で木陰を探しながら我が子を待つ。
大阪にいた頃はイベントなどで小学校に行けば必ず顔見知りがいて、挨拶を交わしたりおしゃべりをしたりしたものだが、さすがに転入してきたばかりのここではそうはいかない。かといって、空気を読まず手当り次第に話しかけると後で後悔しそうなので、無理をせずに機会をうかがうことにした。
しばらく待っていると次男が笑顔で駆けて来た。学校での様子を話してくれる。紙飛行機を作ったとか、ドラムを叩きすぎて手が痛いとか、クールな子がいるとか…彼なりに頑張っているようだ。クラスメイト達も彼にはゆっくり話してくれるらしく、言葉の問題も心配していたよりなさそうでほっとした。学校に慣れる頃には、彼のユーモアも全開でお友達もたくさんできるだろう。
学校がスタートして4日目だが、毎日が「登校してドラムの練習、スナックタイムを挟んでドラムの練習、ランチを取ってからドラムの練習、そして下校」というスケジュール。今日の午後に保護者を招いたドラムの発表会があり、来週から少しずつ教科も入ってくるようだが、アジアから転入してきた子ども達にとっては衝撃だろう。特に日本では新学期が始まる頃になると「子どもの自殺防止キャンペーン」が始まる。それほどまでに「学校」というものがプレッシャーである子は多い。ここカナダでは、少なくとも小学生までは本当にのびのびと生活しているように見える。お弁当とスナック、水筒だけをバックパックに入れて登校する次男の顔からは緊張が消えていた。「クラスメイトに変な日本語を教えてやる」といたずらな笑みさえ浮かべている。仲間はずれとか、いじめとか、そんな心配は取り越し苦労だった。香港に住んでいた頃、インターナショナルの幼稚園に通っていたこともあり、様々な人種の子ども達と交わることに違和感がないのだろう。香港の幼稚園での友達の名前がここにきて時々次男の口から出てくる。イギリス人やドイツ人の古い友人達を今のクラスメイト達から連想したのかもしれない。それはつまり、彼らと友達になれるという気づきでもあると思う。
子ども達が新しい環境に溶け込んでいくスピードは早い。「学校」という所属できる場所があるので、もう既にこの社会の一員だ。私はというと、まだここでの生活スタイルを模索している。自分らしく、そして楽しくここで暮らすために何をすべきなのか。自分を鼓舞して積極的に活動しなければ、すぐにやって来る暗い雨の季節を乗り切れないだろう。
早速、Language Exchangeのサイトに投稿してみた。日本語に興味のある人が意外と多い。さて、どんな出会いがあるのだろう。近い未来さえ想像がつかない毎日は、刺激的だ。
Powered by Froala Editor